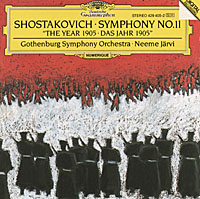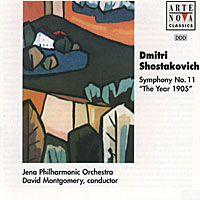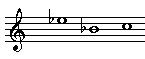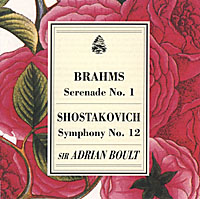名盤(交響曲第10〜12番)
「数学だ、無限の数学だ」。これは、イリヤー・グリゴーリエヴィチ・エレンブールグの小説『雪どけ』の中で、設計技師ソコロフスキイがラジオでショスタコーヴィチの交響曲第10番を聴き、長い沈黙の後につぶやく言葉である。1953年12月17日、レニングラード・フィルハーモニー大ホールにおける、エヴゲーニイ・アレクサーンドロヴィチ・ムラヴィーンスキイ指揮レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団による初演の後、わずか五ヵ月後に発表された小説の中にこのような記述が現れたことは、この作品の反響の大きさを端的に示している。
1953年3月5日、単にソ連の指導者としてばかりでなく、今世紀の最も偉大な権力者であったスターリンが死去した。死後直ちに社会に目立った変化が起きたわけではないが、どことなく解放されたような自由な空気が流れ出した。その後、1956年2月に行われたソ連共産党第20回大会において、スターリン批判の「フルシチョフ秘密報告」と呼ばれる演説がなされるに至り、スターリン時代の反動ともいえる自由な(あくまでもスターリン時代と比べて、ではあるが)時期が訪れる。上記エレンブルグの小説の題名から、この時期は「雪どけ」期と呼ばれる。
交響曲第10番が発表されたのは、この「雪どけ」がまさに始まろうとしていた時期であった。スターリン主義の呪縛から解放されていない者、一方で新たな時代の到来に大きな期待を寄せる者、両者が手探りの状態であった。音楽界では、1953年11月に発表されたハチャトゥリャーンの論文「創作上の大胆さとインスピレーションについて」が大きな波紋を投げかけていた(鹿島・江川編訳:『ソヴェト藝術論爭』, 青木文庫所収)。新しい課題にこたえる作品は「形式の上で美しくなければならない、それらのなかにには、新しい、先進的な芸術の精神が生きていなければならない。それらは大胆な、勇気あるものとなり、それらのうちには不安と動揺がなければならない、『平穏無事が何よりのしあわせ』という精神があってはならない」としたこの論文は、“ジダーノフ批判への叛旗”として騒がれた。この論文に応えるような形で出現したのが本作、交響曲第10番であった。
1945年に発表された交響曲第9番作品70以来、1948年のジダーノフ批判のあおりを受けて、ショスタコーヴィチは体制に迎合するような作品ばかりを発表していた。「ベルリン陥落」作品82、「忘れがたい1919年」作品89、といったスターリン讃美の映画の音楽、「森の歌」作品81、「我が祖国に太陽は輝く」作品90といった体制讃美の声楽入り大編成作品、「革命詩人による10の詩」作品88のような露骨な革命讃美の合唱曲。いずれも作品の出来自体はともかく、ショスタコーヴィチにとって不本意な作品群であったことは間違いない。当時まだ幼い子供を二人も抱えていただけに、こうした体制迎合の作品で日銭をかせぐことは苦渋の選択であったはずだ。スターリンが死去した1953年、ショスタコーヴィチは8年振りに交響曲の筆を取る。作曲はいつもながらの速筆で進められ、第一楽章が8月5日に完成した後、第二楽章が8月27日、第三楽章が10月8日、第四楽章が10月25日に仕上げられている。
ショスタコーヴィチが8年振りに発表する交響曲となったこの作品には発表前から大きな関心が集まり、初演後すぐに様々な反響と議論が巻き起こった。詳細は井上頼豊著『ショスタコーヴィッチ』(音楽之友社, 1957)に紹介されているが、全曲中における終楽章のバランスと作品の持つ悲劇性の2点が主な論点となったこの“第十論争”は、スターリンの死によって引き起こされたソ連社会の思想的・イデオロギー的な混乱と戸惑いを顕著に示している。
作曲家同盟の討論会で、ショスタコーヴィチはこの作品について次のように語っているが、そこにはジダーノフ路線を堅守しようとする保守派に対する慇懃な配慮と、自らの作品が新たな時代を創り出すのだという不敵なまでの自信が入り交じっている:
去年夏にわたしは第十交響曲にとりかかり、秋にはそれを完成した。他の作品同様、わたしはすばやく書きあげた。しかしこれは長所ではなく、むしろ欠点というべきだろう。こんなふうに速く書かれた作品はたいてい不十分なところがたくさんあるからだ。作品を書きおわれば創作熱の消えてしまうような作品の欠点が、ときには大きな、本質的な欠点がみつかり、だがつぎの仕事でそれを克服すればいいだろうと考えかけるときには、書かれたものはもはやおしまいなのだ。
すべての人に、何よりも自分に、わたしは忠告する、急ぐな、と。すこしでも時間をかけて作曲し、仕事の過程ですべての欠点をなおすほうがいい。
この交響曲は四楽章から成っている。第一楽章を批判的に見かえしてみると、つねづね夢みていたような真のアレグロの交響曲を書くことに成功しなかったことがわかった。以前の交響曲でもできなかったが、この作品でもうまく行かなかった。しかしきっと将来、そうしたアレグロを書くことはできるだろう。わたしの交響曲第一楽章は、英雄的・悲劇的(ベートーヴェン、チャイコフスキー、ボロジンその他これに類する作曲家の交響曲第一楽章のような)よりもテンポはおそく、抒情的な要素が勝っている。
第二楽章は、わたしの思うに、がいして構想どおりで、全曲のなかでしかるべき位置を占めている。しかしこの楽章は短すぎる。第一、第三、第四楽章がかなり長いのを考えると特にそうである。こうして全曲の構成にいくらか破綻がおきている。そう大きくない第二楽章とともに全曲の構成を均斉のとれたものにできるもう一つの楽章が不足しているようだ。
第三楽章についていえば、やや冗長なことと、逆に足りないところがありはするが、意図は多少とも達せられていると思う。この点おおかたの意見をきくことは、きわめて有益でもあり貴重でもある。
フィナーレでは序奏部がいくらか長めになっている。最後にきいたときには、それが意味上、構成上の機能をはたしていて、多少とも楽章全体の均衡を保たせているとは思ったが。
作曲家は、自分としてはこうやってみたのだが、などと言いたがるものである。だがわたしはそういうふうに語ることはひかえよう。聴衆が何を感じたかを知り、その意見をきくことのほうが、わたしにははるかに興味ぶかい。ひとことだけいえば、この作品のなかでは、人間的な感情と情熱とをえがきたかったのである。(『ソヴェト音楽』1954年第6号:ショスタコーヴィチ自伝, pp.214-215)
また、「若い作曲家たちに与える」と題された論文の中では、ジダーノフ批判期と同様に数々の批判を受け入れる姿勢を示しつつも、ジダーノフ批判期とは明らかに異なる自分の作品に対する毅然とした態度が表明されている:
交響曲にささげられた今年春のソ連作曲家同盟第八回幹部会総会は、興味ぶかい論議を呼び、その論議のなかで現代交響楽の発展の重要な側面にふれることになった。交響曲のドラマトゥルギーの複雑な諸問題、とりわけいわゆるフィナーレ問題が論議された。総会で演奏された大部分の交響曲で、最初の三楽章にくらべフィナーレが成功していないことが注目の的となった。
すべての人に、何よりも自分に、わたしは忠告する、急ぐな、と。すこしでも時間をかけて作曲し、仕事の過程ですべての欠点をなおすほうがいい。
どうしてフィナーレがつまらないのか。フィナーレを書くのは、第一楽章やアダジオを書くよりむずかしいだろうか。わたしははからずも、ブラームスのたいへん単純だが賢明な言葉を思いだした。作曲家のブルックナーが彼に、交響曲のすぐれたアダジオを書くのはなかなかむずかしいと言ったとき、ブラームスは、「自分には、交響曲全体、全楽章をきちんと書くことのほうがはるかにむずかしい、アダジオにとどまらず」と応えたのは至極当然だった。
それだけでなくわたしには、交響曲のどの楽章を書くことも容易でない。作曲家は交響曲全体が、芸術的に完璧なものになるよう、努力して書かなければならない。
……一連の批判的演説の中で、わたしの第十交響曲のフィナーレにいくらかドラマトゥルギーの不完全なことが指摘された。この指摘はまったく正しいと思う。この交響曲のフィナーレの音楽は、全体として完了してはいたが、それでも何かが不足しているようだ。明らかにここには、大きい旋律的呼吸をもつ対照的テーマが欠けていた。このフィナーレには、速い活発なテーマが勝っているが、そのほかに、もっとゆったりとした、歌うようなテーマを、まん中あるいは終りちかく、むしろいちばん最後におくべきだった。そうすれば、それがフィナーレと交響曲全体の響きをもっと強めたろう。交響曲の最終楽章を書きなおすか、まったく新たに書くべきだったろうか。いつかはそうするかもしれないが、それは今すぐにではない。作品は全体として構想され、つくられたものであって、もう一度そこに帰って行くのは今はなんとしてもつらいのである。
若い作曲家に切に望みたいことは、自分の作品にむけられたまじめな批評に残らず耳をかたむけることである。自分自信は残念ながら、常にそうできるわけではなかった。失敗作を、改作したり訂正したりすることはほとんど不可能だった。うまく書けなかったものは、そのままになった。失敗はその後の作品のなかで正していこうとした。いまになってみると、それはそう正しくなかったことがわかってきた。自分の作品は、それを書いた作者の責任で扱わなければならない。弱い、不十分なところがあれば、それを批判的に検討し、書きなおさなければならないのである。
……音楽をつくること、それは軽い遊びではなく、きわめて真剣な、苦しい仕事だ、とことあらためて言う必要があるだろうか。てがるに、てばやく、ろくに考えもしないで作品を書く作曲家をわたしは知っているが、その結果はろくなものにならない。真の芸術家は、自分の作品に精魂こめてたちむかい、軽率な、あるいは無思慮な功利主義をもって対したりはしないものである。
……誠実な音楽家なら誰でも、自分の作品に騎士のごとき高潔な態度をとるべきである。意識して質のひくい作品をとどけるような芸術家は、人民にたいしても、自己にたいしても不誠実きわまりない。
……わたしは、自分の作品について、とくに交響曲についてどう思っているかとたずねられることがある。そういうときはたいてい、古いロシアのことわざで答えることにしている。「子どもは片目でも親にとってはかわいい」。自分の作品はずいぶん欠点が目についても、なおかわいいものである。もし自分の作品を愛せず(その作品にたいする批判的太緯度を排するということではない)、汗の結晶に冷淡だとしたら、そこからは何も生れてこない。だからわたしは自分のほとんどすべての作品に、ときに重大な欠陥のあることがわかっても、概して好意的な態度をとっているのをかくそうとはしない。自分の作品のなかに欠陥をみることをやめてしまった作曲家は、そこで進歩がとまって足ぶみする以外にはない。(『ソヴェト音楽』1955年第10号:ショスタコーヴィチ自伝, pp.227-232)
こうした論争は、スターリンの死に伴うソ連国内体制の変化とも結び付けられ、ソ連国外においても様々な憶測とともに受け止められた。国外初演権を巡る争いなどのエピソードに、この作品の注目度の高さを伺うことができる。しかし、このような政治的背景に対する興味だけでは芸術作品として生き残ることはできない。この作品が現在に至るまで頻繁に取り上げられていることは、当時の批判に反して、堅固な構成と深い内容に加えて魅力的な抒情性を持っていることの証左だと言える。
もう一つ。この作品の構成には際立った特徴があり、作曲家の吉松隆氏がリストのファウスト交響曲と関連づけて分析している。第1楽章冒頭の低弦の動機と「ファウストの主題」、第二主題と「ファウストの闘争の主題」、第2楽章冒頭の動機と「メフィストの動機」などの顕著な類似から、第1楽章を「ファウスト」、第2楽章を「メフィスト」、第3楽章を「グレーチェン」に対応させことができるとしている。ショスタコーヴィチの音名象徴「DSCH」が頻出する第3楽章の中でホルンに12回も出てくる「E-A-E-D-A」音型については、一柳富美子氏によって、モスクワ音楽院の教え子エリミーラ(ЕЛМИРА)・ナジーロヴァの署名だという説が主張されている(Е=E、Л=A、МИ=E、Р=D、А=Aということ)。これらのことから、「ファウスト=ショスタコーヴィチ」、「メフィスト=スターリン」、「グレーチェン=ナジーロヴァ」という対応をもった自伝的作品だとする解釈が、現在では主流になってきている。何でもかんでもスターリンや当時のソ連体制と結び付けるのは筆者の好みではないが、この作品にファウスト伝説を下敷きにしたスターリン(体制)に対するショスタコーヴィチの精神的な葛藤の跡を見い出すことは決して難しくないだろう。
交響曲第5番に次いでよく取り上げられる作品だけに数多くの録音があるが、カラヤンの4種類の録音が最高峰である。幅広いレパートリーを誇ったカラヤンだが、ショスタコーヴィチの交響曲はこの第10番ただ一曲しか取り上げなかったということは面白い。まず筆頭に挙げられるべきはカラヤン/ベルリンPO(DG)の1981年盤だろう。これはもう非の打ち所がない完璧な名演。ライヴ録音で聴かせる狂気に満ちた恐怖感はあまりないものの、オーケストラの圧倒的な技量に裏打ちされた全く隙のない仕上がりは他の追随を許さない。解釈も最良の意味でスコアに忠実なもの。憎らしいまでの巧さと、壮大な余裕がこの作品に一層の風格を与えていることにも注目したい。カラヤンのスタジオ録音に顕著な人工臭がことごとくプラスの方向に作用した稀有の例といってもよいだろう。カラヤンの厖大な録音の中でも間違いなくトップクラスに位置づけられる名盤と言えるだろう。1981年盤の完成度は驚異的だが、突き抜けた音楽的内容を持つのは、1976年のザルツブルク音楽祭におけるカラヤン/ドレスデン・シュターツカペレ(Sardana)盤である。第1楽章の400小節から427小節までが欠落しているが、これは単なる編集ミスではないようで、なぜこの演奏においてのみカラヤンがこうした不自然なカットを採用したのかは不明。演奏は、カラヤンの生演奏がいかに凄かったかを実感させてくれるもの。極めて巧みなデュナーミクの扱いから生み出される息の長いフレーズの中に、凶暴なまでのエネルギーが盛り込まれている。聴き手はただの一瞬も息をつくことができない。ほとんど共演する機会がなかったであろうドレスデン・シュターツカペレも、カラヤンの棒に対して恐ろしいまでの一体感を持って反応している。これほどまでに滅茶苦茶な恐怖を感じさせる演奏もないだろう。海賊盤のために音質等の不満はあるものの、これを聴き逃す手はない。ショスタコーヴィチ自身も臨席したカラヤン/ベルリンPO(Melodiya)の1969年モスクワ公演のライヴ盤も凄い。カラヤン壮年期の演奏スタイルが、最上の形で結実した名演。ギラギラするような覇気に満ちた、細部まで完璧にコントロールされた仕上がりは、他の追随を許さない。もちろんライヴならではの些細な瑕はあるのだが、表現したいことが全て音になっている爽快さは格別。オーケストラの中から湧き出てくるような壮大なうねりは、小手先の技では決して再現し得ない作品の本質を暴き出している。録音が悪く、音がモゴモゴしているのが残念だが、演奏そのものは最高級のものである。もちろん、カラヤンがこの曲を最初に取り上げたカラヤン/ベルリンPO(DG)の1966年盤も全く不満のない素晴らしい内容。ベルリン・フィルが異様に高いピッチをとっていた時期の録音で、一瞬調性感がおかしくなったような気がするが、ド派手な響きと豪快な推進力、嫌味なまでの名技のひけらかし、憎らしいまでの表現の巧さ、いずれをとっても当時このコンビが持っていた潜在能力を全て発揮しきった名演。有無を言わさぬ説得力を持っている。
初演者ムラヴィーンスキイも同じく4種類の録音を残しているが、初期の演奏には若干不満が残る。しかし、1976年3月の3日と31日に収録された2つの録音は文句無しに素晴らしい。ムラヴィーンスキイ/レニングラードPO(Victor)による3月3日の録音は、異常な完成度を持った緊張感あふれる名演。テンポの揺れなどは最初のスタジオ録音からほとんど変わっていないが、全てがムラヴィーンスキイの様式としてこなれており、不自然さを感じさせない。楽器間のバランスもライヴとは信じられないほど整えられていて、理想的な響きがしている。早目のテンポの中に漂う尋常ではない厳しさが、曲の格調を一層高めている。31日の録音も、当然のことながらほぼ同じ仕上がりである。録音状態も似たようなものであり、優劣をつけることはできない。筆者の耳にはこちらの方がやや緊張感に勝るように聴こえるが、その違いは微々たるもの。ムラヴィーンスキイでこの曲を聴くのなら、これら2種のライヴ盤を選ぶべきである。
ハイティンク/アムステルダム・コンセルトヘボウO(Q Disc)の1985年ライヴ録音も凄い出来。ハイティンクによる全集に収録されたロンドンPOとの旧盤と同じつもりで聴くとヤケドをしてしまうような演奏。旧盤と異なって手兵であるコンセルトヘボウ管とのライヴ録音ということが、あらゆる面においてプラスに作用している。あくまでも純器楽的なアプローチを保っているところはいかにもハイティンクらしいが、演奏の熱気がもの凄い。ライヴならではの瑕はあるものの、格調の高さと壮大さは比類なく、曲の隅々まで完璧に理解したという自信すら感じられる踏み込みの凄まじさに圧倒される。14枚組という大きなセットに収録されているが、この1曲だけのために買う価値がある。こうした凄絶な演奏に対して、フェドセーエフ/モスクワ放送SO(Relief)の新盤は格調の高い個性的な名演。旧盤同様に抒情的な音楽の運びが特徴的だが、旧盤に見られた荒っぽさはなく、磨き上げられたオーケストラの機能美にも目をみはるものがある。ムラヴィーンスキイの胃の痛くなるような緊張感よりは、カラヤンの壮麗さに近いものを感じるが、加えてスラヴ的な旋律の歌い回しとロシアン・ブラスの音色が極めて魅力的。思いの外トランペットが突出しないのが、フェドセーエフの新境地か。しなやかな弦楽器も素晴らしいが、完璧な木管楽器が凄い。
アンチェル/チェコPO(DG)盤は、フランスでのみCD化されているが、これも必聴の名演。恐ろしい音楽。録音(あるいは復刻)の影響もあるのだろうが、チェコPOとは思えないささくれだった音がいかにもこの曲にふさわしい。第1楽章のクライマックスの金管の叫びには、背筋の凍るような思いをさせられる。全編に渡って攻撃的な音楽が繰り広げられるが、表現の懐は実に深く、一本調子に陥ることがないのも素晴らしい。両端の音域が強調された痩せた録音が残念だが、演奏本位で考えると間違いなくトップ・クラスの演奏である。
上記4者の名演と比べるとやや落ちるものの、人気の高い名作だけにこの他にも素晴らしい演奏がめじろ押しである。コンヴィチュニー/ライプツィヒ・ゲヴァントハウスO(Berlin Classics)盤は、典型的なドイツの音色とオーソドックスな解釈、特に奇を衒った部分は皆無なのに、とてつもなく恐ろしい響きがしている個性的な演奏。弦楽器は悲鳴をあげ、管楽器は威嚇するような鋭い咆哮を唸りあげる。当時の旧東ドイツだからこそできた演奏なのだろうか?録音状態や技術的な完成度はやや劣るものの、ファンならば聴き逃すことのできない一枚。同じ系統としては、異様にゴツゴツしたアーティキュレーションが不安感を煽る、ミトロプーロス/ニューヨークPO(CBS)盤の戦慄に満ちた秀演も忘れるわけにはいかない。各楽章のクライマックスにおける緊迫度は群を抜いている。録音が優れないのが残念だが、この硬派さは捨てがたい。妙にテンションの高いクルツ/フィルハーモニアPO(Testament)盤も聴き応えがある。全体を通して、オーケストラが悲鳴をあげているかのように聴こえる。クライマックスでの爆発力は並外れている。アンサンブルやピッチの乱れなどが気にならなくもないが、それを超えて有無を言わさず迫ってくる恐怖感が傑出している。
こうした聴き手に過大な緊張を強いる演奏に対し、ゆったりと構えた演奏にも優れたものがある。代表的なものとして、プレヴィン/ロンドンSO(EMI)盤が挙げられるだろう。無理のないオーケストラの響きと自然な音楽の流れはプレヴィンのショスタコーヴィチ演奏の特徴だが、この作品ではそれに加えて情熱に満ちた勢いが感じられる。戦慄が走るような凄みとは無縁だが、いやが応にも聴き手を引き込むような音楽の力に満ちている。終楽章の解放感と華やかさは格別。陽性の解釈の中では傑出した演奏である。デプリースト/ヘルシンキPO(Delos)盤も決して派手ではないが、すみずみまで丁寧に磨き込まれた秀演。オーケストラに無理をさせず、しかしながら引き締めるべきところはきちんと押えた演奏は、スケール大きな歌心に満ちた音楽を実現している。特に和声の扱いは秀逸で、勢いだけではない確かな譜読みを窺わせる。息詰るような緊張感はないが、単に壮麗なだけではない充実した仕上がり。K. ザンデルリンク/ベルリンSO(Deutsche Schallplatten)盤は、いつもながらの非常に渋い味わいを持った秀演。鋭く突き刺さるようなタイプの演奏とは異なり、ゆったりとしたスケール大きな音楽の中に内容がぎっしりと詰まっている。第1楽章のクライマックスでドラの音が割れるのが残念だが、表面的な悲劇にとどまらない確信に満ちた音楽は大変充実している。一方、スクロヴァチェフスキイ/ハレO(IMP)盤は流麗な音楽の流れが印象的な秀演。随所に個性的な楽器バランスの取り方が聴かれるが、全体のフォルムを崩すようなものではない。圧倒的な緊張感や力強さ、コクとは全く無縁だが、徹底して音響を楽しむようなスクロヴァチェフスキイの演奏は独特の説得力を持っている。
人気の高いN. ヤルヴィ/スコティッシュ・ナショナルO(Chandos)盤は、実に若々しい勢いに満ちた好演。弦楽器がやや弱いものの、ショスタコーヴィチ特有の音色をよく踏まえた管楽器が冴えている。両端楽章のクライマックスへと突進する勢い、第2楽章の爆発力、いずれもさほど深みはないものの実に爽快。第3楽章ではこの演奏の底の浅さを露呈してしまうのが残念だが、十分に曲の魅力を伝える演奏と言えるだろう。
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
カラヤン盤
(DG 413 361-2) | カラヤン盤
(Sardana sacd-203/4) | カラヤン盤
(Ars Nova ARS 008) | カラヤン盤
(DG 429 716-2) | ムラヴィーンスキイ盤
(Victor VDC 25027) | ムラヴィーンスキイ盤
(Victor VICC-40118/23) | ハイティンク盤
(Q Disc 97014) | フェドセーエフ盤
(Relief CR 991047) | アンチェル盤
(DG 463 666-2) |
 |  |  |  |  |  |  |  |
|
コンヴィチュニー盤
(Berlin Classics 0090422BC) | ミトロプーロス盤
(CBS MPK 45698) | クルツ盤
(Testament SBT 1078) | プレヴィン盤
(EMI CDD 7 64105 2) | デプリースト盤
(Delos DE 3089) | K. ザンデルリンク盤
(Deutsche Schallplatten
32TC-83) | スクロヴァチェフスキイ盤
(IMP PCD 2043) | N. ヤルヴィ盤
(Chandos CHAN 8630) |
1957年夏頃から本格的に作曲に着手し、同年8月4日に完成した。初演は1957年10月30日、モスクワ音楽院大ホールにてナタン・ラーフリン指揮ソヴィエト国立交響楽団によって行なわれた。続く11月3日には、エヴゲーニイ・アレクサーンドロヴィチ・ムラヴィーンスキイ指揮レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団によってレニングラード初演が行なわれている。作曲者自ら「10月革命40周年記念」と書き込まれたこの交響曲は、同年のレーニン賞を受賞した。
その悲劇的な曲調が、雪解け直前の楽壇に議論を巻き起こした交響曲第10番作品93からおよそ4年。注目されたショスタコーヴィチの新しい交響曲は、ロシア第一次革命という政治的な意味を多分にもった叙事的描写音楽であった。この作品に対するショスタコーヴィチ自身のまとまったコメントは、意外にも次の一つだけである:
いまわたしは第十一交響曲をつくっているが、冬までにはたぶん仕上がると思う。テーマは一九〇五年の革命である。労働者の革命歌にあざやかにうつされている祖国のこの時代がわたしはたまらなく好きだ。これらの歌の旋律をひろく交響曲にとりいれるかどうかはわからないが、この交響曲は性質上ロシアの革命歌にごく近いものとなる。(『ソヴェト音楽』1956年第9号:ショスタコーヴィチ自伝, p. 260)
1957年といえば、10月革命40周年の記念の年であり、こうした革命讚美の大交響曲が当局の望むものであったことは、ほぼ間違いない。それゆえに、交響曲第10番で新しい境地を開いたショスタコーヴィチが、再び体制に迎合したとして特に西側では批判されることとなった。
しかしながら、当時の社会情勢およびショスタコーヴィチの社会的地位を考えると、必ずしも体制迎合であるとばかりは判断できない。前年に生誕50年を祝ってレーニン勲章を授与された彼にとって、ここで標題性を持たない純器楽の交響曲を発表することは決して不可能なことではなかっただろう。とはいえ、10月革命の記念に1905年の「血の日曜日」事件を題材とし、「この時代がわたしはたまらなく好きだ」と述べている辺り、当局からの強い要請を断わりきることができず、テーマを若干逸すことによってささやかな抵抗を試みたのだと邪推することもできる。結果として、10月革命を扱った交響曲も作らざるを得なくなり、交響曲第12番作品112が誕生することとなったのかもしれない。いずれにしてもこの2作品は、各楽章につけられた副題や形式、規模といった点で姉妹作といってもよい関係にある。
各楽章の副題は次の通り:第1楽章「Дворцовая площадь(宮殿前広場)」、第2楽章「9 января(1月9日)」、第3楽章「Вечная память(永遠の記憶)」、第4楽章「Набат(警鐘)」。楽曲の印象はほぼ副題に忠実で、「血の日曜日」事件にまつわる各種のエピソードを生々しく想起させる。特に第2楽章第2部の“血の日曜日”を描写した部分の凄惨さは圧倒的。群衆の叫びと無情な銃声とが、これ以上ないまでにリアリスティックに表現されている。
加えて、数々の革命歌の引用が(おそらく当時のロシア人にとっては特に)効果的で、「1905年」という曲の標題により分かりやすい真実味を加えている。引用されている革命歌は以下のもの:
- 『聞いてくれ!』(第1楽章練習番号8)
- 『夜は暗い』(第1楽章練習番号16)
- 『おぉ、皇帝われらが父よ』(第2楽章練習番号28:「革命詩人による10の詩」作品88第6曲からの引用)
- 『帽子をぬごう』(第2楽章練習番号41:「革命詩人による10の詩」作品88第6曲からの引用)
- 『同志は倒れぬ』(第3楽章練習番号99)
- 『こんにちは、自由よ』(第3楽章練習番号108)
- 『圧政者らよ、激怒せよ』(第4楽章練習番号121)
- 『ワルシャワンカ(ワルシャワ労働歌)』(第4楽章練習番号140)
この他、弟子のゲオルギイ・ヴァシーリエヴィチ・スヴィリードフのオペレッタ「ともしび」から『雷鳴の夜はなぜつらい』も引用されている(第4楽章練習番号146直前)。(このような親しみやすい旋律に満ちているのは、この作品の題材が大衆性を求めているということだけではなく、当時のショスタコーヴィチの作品全般に共通する傾向でもある。当時ショスタコーヴィチは、二番目の妻マルガリータ・アンドレーエヴナ・カーイノヴァとの(不幸な結果に終わった)結婚生活を送っていた。カーイノヴァは音楽的素養のない女性だったらしく、弦楽四重奏曲第6番作品101のような分かりやすい作品は、カーイノヴァの存在を考慮していたとも言われる。)
これだけの材料が揃っていれば、“革命讚美”“体制迎合”の作品と判断されるのは致し方のないところだろう。少なくとも非共産圏においては、このような作品が誕生する可能性は皆無と言っていい。しかしながら、それにしてはあまりにも悲劇的な曲調に終始するところに、多少の引っ掛かりを感じるのは当然だろう。確かに最初の3つの楽章は人民の悲劇的なエピソードを扱っているものの、終楽章は来る10月革命に向けて、そしてその革命の成就を予感させるような希望に満ちた音楽でもおかしくはないはずだ。実際にどうだったのかは分からないが、この作品を聴いて“10月革命を題材にした壮麗な続編”が発表されることを当局が期待したとしても当然だろう。
この作品が純粋に1905年の「血の日曜日」事件を描いたものなのか、それとも当時のエピソードにショスタコーヴィチ自身が生きた時代(1956年には、ハンガリー動乱が起こっている)を重ね合わせたのか、それはショスタコーヴィチ自身しか知らないことである。とはいえ、どこか解決しきらない最後の鐘の響きを聴くと、単なる体制寄りの作品と捉えるのはあまりに浅薄な解釈ではなかろうか。また、ショスタコーヴィチの手腕が遺憾なく発揮されたオーケストレイションも聴きもので、長さをそれほど感じさせない緊密な構成も含めて、“続編”交響曲第12番作品112とは異なる優れた作品でもある。
その題材故か、録音はあまり多くない。また、最近の録音は当然ながら古いソ連の録音よりも音質は優れているのだが、筆者にはダイナミックレンジの広さが逆にわずらわしく感じられる。第1楽章や第3楽章の弱音部にヴォリュームを合わせておくと、第2楽章や第4楽章の強奏部で鼓膜が破れそうになる。逆に合わせると、曲の大半が何も聴こえない。実際の演奏会場ならば問題にならないのだろうが、ノイズに満ちた貧弱な我が家で聴くとなると、優れた録音がかえって鬱陶しい。
以上のことも踏まえた上で、まず筆頭に挙げなければならないのはムラヴィーンスキイ/レニングラードPO(Melodiya)のスタジオ録音。これは極めて風格のある格調高い演奏。全てが磨きあげられ、考え抜かれた緻密な設計の元に積み上げられた感がある。録音の鮮度は悪いが、この曲の理想的な再現だといえよう。同コンビによるレニングラード初演の歴史的なライヴ録音(ムラヴィーンスキイ/レニングラードPO(Russian Disc))もある。録音状態はあまり良くないが、歴史的価値は非常に大きい。ムラヴィーンスキイの別の録音に比べて3楽章以外のテンポが非常に早く、狂気に満ちた音楽となっている。特に4楽章の狂暴さは異常。ムラヴィーンスキイは、このスコアの中に何を見い出していたのだろうか?
ムラヴィーンスキイに劣らず、むしろ録音状態も含めるとその上をいくと言ってもいいのがベリルンド/ボーンマスSO(EMI)盤。これは素晴らしい。標題音楽的な迫力に欠けることなく、交響曲としての魅力を完璧に表出している。堅実かつ適切なテンポ設定で、オーケストラが全く無理なく鳴りきっている。すみずみまで磨き上げられたアンサンブル、気品がありながらも心のこもった歌い回し、いずれをとっても全く不満がない。この曲の良さが分からない聴き手には、まず最初に聴いてもらいたい演奏。ロシア勢による演奏としては、ロジデーストヴェンスキイ/ソヴィエト国立文化省SO(Melodiya)盤も優れている。第2楽章の中間部は極端に遅いテンポだが、それ以外はむしろ早目の引き締まったテンポ。それでいて全体に重厚な仕上がりで、芝居がかったこの曲の内容を余すところなく引き出した名演。過度に悲劇的にも英雄的にもならず、ひたすら音響を積み上げていく解釈はこの曲にふさわしい。時としてかなり荒っぽい演奏をするコンビだが、ここではかなり精密なアンサンブルを見せている。もちろん、金管楽器や打楽器のアクの強い響きは健在。
非常に個性的なのが、コンヴィチュニー/ドレスデン・シュターツカペレ(Berlin Classics)盤。これほどまでに聴き手に恐怖を感じさせる演奏は他にない。全ての楽器の音色が、心に突き刺さってくる。引き締まったテンポの中で、どこかぎこちないフレージングが異様に意味深い。技術的な完璧さや録音の優秀さとは無縁だが、極めて個性的で、しかし曲の本質をしっかりと掴んだ名演。この演奏を聴いて、この曲を“革命讚美”などと受け取る人はまずいないだろう。
上記5点に比べるとやや落ちるが、立派な演奏が他にもある。デプリースト/ヘルシンキPO(Ondine)盤は、標題音楽としての側面を押し出さずに、徹底して交響曲として仕上げた秀演。ゆったりとしたテンポで、決して刺激的な音響に溺れることなく、丁寧にスケール大きな音楽を奏でている。オーケストラの響きはいかなる箇所でも澄んでおり、力任せになることがない。猛烈な演奏を嗜好する向きには物足りないだろうが、実に格調の高い立派な演奏である。同系統の演奏として、ハイティンク/アムステルダム・コンセルトヘボウO(London)盤も挙げられよう。非常に誠実な演奏で、オーケストラは最高水準の技術とまでは言い難いが、実に丁寧かつ清潔に演奏に取り組んでいるのが気持ち良い。標題音楽としての側面ばかりが強調されがちな曲だが、ハイティンクの純器楽曲的なアプローチはムラヴィーンスキイにも通ずるところがあり、曲の真価を適切に伝えている。それでいて興奮にも不足しないところが素晴らしい。ただ、個人的にはあと一歩の透徹感を望みたいところ。また、ストコーフスキイ/ヒューストンSO(EMI)盤が、ストコーフスキイにしては驚くほど真っ当な演奏で面白い。現代作品の紹介に対するストコーフスキイの態度を垣間見ることができる。強烈なロシア色を感じさせず、いわゆる西側風の洗練された響きの中で、交響曲としてのこの曲の真価を丁寧に表出している。もちろん、コンドラーシン/モスクワPO(Melodiya)盤も、いつもながらの力感に満ちた演奏で悪くない。やや早目のテンポで颯爽かつグイグイと押していくスタイルには、素直に昂揚させられる。特に第4楽章の仕上がりが立派。ただ、このコンビの他の演奏に比べると、全体にスマートにまとまり過ぎのようにも感じられる。
新しいところでは、ロストロポーヴィチ/ナショナルSO(Teldec)盤を忘れてはならない。これは、やや粘着質の重厚な秀演。全ての音に質量が感じられるような演奏で、特に第2楽章の虐殺の部分の遅さは聴き手によって好みが分かれるだろう。このコンビにありがちな荒っぽさはあまりなく、丁寧な仕上げといってもよい。第1楽章などの弱奏部における表現力には若干の不満を感じなくもないが、強い意欲に貫かれた巨大な音楽はなかなか魅力的。最後の鐘はわざわざ特注したものらしく、異例なまでに長い残響は、ロストロポーヴィチのこの曲に対する独特の思い入れを窺わせる。
オーケストラの技量に若干の不満がなくもないが、N. ヤルヴィ/エーテポリSO(DG)盤、モンゴメリー/イェーナPO(Arte Nova)盤も決して悪くはない。
 |  |  |  |  |  |
ムラヴィーンスキイ盤
(Victor VICC 40118/23) | ムラヴィーンスキイ盤
(Russian Disc RDCD 11157) | ベリルンド盤
(EMI 7243 5 73839 2 9) | ロジデーストヴェンスキイ盤
(Victor VICC-40001/11) | コンヴィチュニー盤
(Berlin Classics 0090422BC) | デプリースト盤
(Delos DE 3080) |
 |  |  |  | 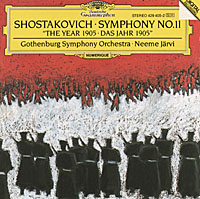 | 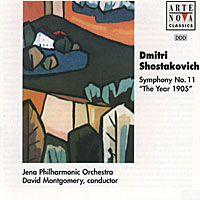 |
ハイティンク盤
(London POCL-9255/66) | ストコーフスキイ盤
(EMI CDM 7243 5 65206 2 2) | コンドラーシン盤
(Victor VICC-40094/103) | ロストロポーヴィチ盤
(Teldec WPCC-5344) | N. ヤルヴィ盤
(DG 429 405-2) | モンゴメリー盤
(Arte Nova 74321 54452 2) |
1961年8月22日に作曲が完了し、第22回党大会の開会日である10月1日、レニングラード・フィルハーモニー大ホールにおいてエヴゲーニイ・アレクサーンドロヴィチ・ムラヴィーンスキイ指揮のレニングラード・フィルハーモニー管弦楽団により初演された。また、その数時間前にショスタコーヴィチが大祖国戦争中に疎開していたクーイブィシェフでもアブラーム・スタセーヴィチによる指揮で同時初演されている。ちなみに、作曲家同盟での試演はモイセーイ・サムイーロヴィチ・ヴァーインベルグとボリース・アレクサーンドロヴィチ・チャイコーフスキイによる2台ピアノで行なわれた。
同じく標題付の交響曲である前作第11番作品103と結び付きの強い作品とされ、ショスタコーヴィチの弟子であったオレスト・エヴラーホフは、「第十二交響曲は、そのイメージ構成と調音の源の点とで第十一交響曲と緊密な関係がある。第十一交響曲同様主な登場人物は、偉大なレーニンによって解放のたたかいを鼓舞され、十月社会主義大革命に勝利をおさめた人民である」(『レニングラード・プラウダ』)と述べている。確かに、革命と密接に関連する標題、描写音楽的な4楽章構成、革命歌の引用、壮麗なオーケストレイション等、外面的な類似は否定することができない。
第1楽章「Революционный Петроград(革命のペトログラード)」、第2楽章「Разлив(ラズリーフ)」、第3楽章「Аврора(アウローラ)」、第4楽章「Заря человечества(人類の夜明け)」と各楽章に標題がつけられ、交響曲第11番ほど直接的な描写性は見られないものの、十月革命にまつわる数々のエピソードを十分に想起させ得る作りになっている。
ショスタコーヴィチ自身は、この作品について次のように語っている:
いまわたしは第十二番目の交響曲にかかっている。一九五七年にわたしがロシア第一革命を記念する第十一交響曲を書いたのをご存じのかたもおありかと思う。それを書きあげたとき、はやくもわたしはその続編を考えはじめていた。こうして第十二交響曲の構想が芽ばえたが、それは十月社会主義大革命を記念するものとなるはずであった。四つの楽章のうち、二つはすでにほとんど完成をみている。この仕事は二、三カ月もすれば終わるだろうと思う。
構想は十分熟しているので、第十二交響曲について、その仕事ちゅう自分を興奮させ、完成するまで興奮させつづけるにちがいない内容、思想について語ることはできる。
もちろん、十月社会主義大革命を記念する交響曲をつくる仕事は決して容易なものではない。この作品が、せめてある程度このテーマの規模と意義にふさわしいものとなるよう、わたしは自分の全知全能をかたむけている。十月革命をテーマとする作曲をしていると、なによりもまず、勤労者の偉大な領袖ウラジーミル・イリイチ・レーニンの姿が浮かんでくるのはごく自然だといえよう。したがって、この交響曲は、偉大な十月とレーニンを等しく偲ぶものとなるだろう。
お知らせしたとおり、交響曲は四楽章から成っている。構想では、第一楽章はレーニンが一九一七年四月ペトログラードに帰還し、勤労者、ペトログラードの労働者階級と出会う音楽物語となるだろう。第二楽章は十一月七日の歴史的事件が再現される。第三楽章は国内戦を、第四楽章は十月社会主義大革命の成就を語るものとなる……。
自分の作品のことを語るのはむずかしいが、この新作交響曲のテーマはわたしを極度に興奮させている。そしてこの作品は、自分の創作歴のなかでも重要な段階を劃するものとなるだろうと思う。自分としてはこの作品をたいへん重視している。
この重要な課題をしとげるのに自分の支えとなるものは何だろうか。わたし自身が十月革命の生証人であり、レーニンがペトログラードにもどってきた当日、フィンランド駅前広場でレーニンその人の演説を聞いた人びとのなかにわたしもまじっていたのである。そのころわたしはたいへん若かったが、このことは永遠に記憶に刻みつけられている。むろん、忘れえぬこの日の思い出が、交響曲の仕事をするについてわたしの支えとなってくれるにちがいない。(『音楽生活』1960年第21号:ショスタコーヴィチ自伝, pp. 311-312)
また、初演後には次のようにも語っている:
この〔第十二〕交響曲は、ロシア第一革命を記念する第十一交響曲の続編のようなものである。ここでわたしは、十月大革命とその領袖レーニンのイメージを具象化しようとした。交響曲は彼を偲ぶものとなる。(『ソヴェト音楽』1961年第7号:ショスタコーヴィチ自伝, p. 320)
これらの(本人が語ったとされている)文章は、交響曲第5番作品47以降、繰り返しその構想だけが語られ続けた幻の“レーニン交響曲”を想起させる:
このレーニンについての交響曲は、合唱団、ソロの歌手、朗読者なども参加する四楽章の作品にしようと考えている。第一楽章はレーニンの青年時代、第二楽章は十月革命を率いるレーニン、第三楽章はレーニンの最期、第四楽章はレーニン亡きあとレーニン主義の道を歩む、となる。音楽的断片はすでにいくつか準備されている……(『レニングラード・プラウダ』1939年8月28日号:ショスタコーヴィチ自伝, p. 96)
ショスタコーヴィチは、同種の発言を繰り返し行なったが、実際にレーニンを主題とした作品が手がけられた形跡は全くない。また、交響曲第12番発表後もレーニンを主題とした新しい作品への意欲を発言している。これらのことから、レーニン讚美の大規模な作品が当局からの強い要請であったことが窺われる。
こうした極めて政治色の強い作品がショスタコーヴィチの共産党入党と時期を合わせて作られたこと、次の作品が逆に政治的に大きな問題を投げかけた交響曲第13番作品113であること、そして、作品そのものの出来が他の交響曲と比べると決して優れているとはいえないことから、この交響曲はいわゆる“体制に迎合した駄作”という評価を受けてきた。ショスタコーヴィチ研究の第一人者サビーニナは、雑誌『Melos』上で次のように語っている:
〔ショスタコーヴィチが一九三〇年代からレーニンを題材とした交響曲を書くように説得されていたが、《第十一番》を書いた後、またまた同じことをしつこく勧められた。〕とうとう彼は屈服して、わたしの知る限りでは、二週間後に生気のない、気の抜けたスコアを書き上げた。《第十一交響曲》には、まだいくつか感動的な素材がある。例えば、第三楽章の平和的な示威行進に対して発砲する場面の描写は、ソ連の大量処刑、つまりスターリンの報復を連想させるし、革命前の重労働や流刑を歌う革命歌の旋律を引用している第一楽章は、『グラーグ〔強制労働収容所〕』の犠牲者や、ラーゲリや監獄で死んだ何百万という人々を思い出させる。ところが、《第十二交響曲》は十月を讚えることを目的としていた。これはショスタコーヴィチのもっとも苦々しい妥協作の一つである。幸せなことに、映画やカンタータはすっかり忘れられてしまったが、《第十二交響曲》は彼の交響曲のリストに入っていて、厳粛な記念祭のプログラムにも含まれる。(ショスタコーヴィチ大研究, p. 123)
このような評価に一石を投じたのが、一柳氏による音名象徴の指摘である。これは、第一楽章再現部直前(407小節)から、曲が進むに従って非常に目立ってくる「Es-B-C」という音型(譜例12‐1)が、スターリンの音名象徴であるというもの。
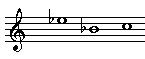
譜例12‐1
スターリンの名前のキリル文字表記は「Ио(Ё)сиф Виссарионович Сталин」であるが、この頭文字をそのままドイツ音名読みすると、譜例12‐1の音型ができあがる。自らレーニンを偲ぶものとしたこの作品の中に、スターリンの象徴が埋め込まれ、それが楽章を追う毎に前面に出てくることの文学的意味は、改めて説明するまでもないだろう。しかも、最後はスターリンの音名象徴「Es-B-C」に被さるようにして鳴り響く、ショスタコーヴィチのイニシャル「D-Es」のトリルで曲を閉じるのである。
この他、何の感動もなく、さりげなく突入する第4楽章の冒頭では「Dies Irae」も聴こえる。壮麗な金管楽器の元で、あたかも悲鳴をあげているかのような弦楽器の響きを聴くと、この楽章が「人類の夜明け」と題した「最後の審判」を描写しているとも解釈できるだろう。ちなみに、ここで用いられている「Заря」という単語は、“夜明け”と同時に“日没”も意味する。
革命歌や「ハレルヤ」などの引用だけではなく、これらの実に周到な仕掛けに気づくことによって、この作品が単なる“体制に迎合した”だけのものではないことが分かるだろう。ただ、率直に言って、曲そのものはやはり名作とまでは言えないというのが筆者の考え。例えば第2楽章などはどんな演奏を聴いても退屈してしまう。体制迎合だろうが反体制だろうが、面白くないものは面白くない(そんなこと言うなら、お前が書いてみろ、と言われても困りますが…(^^;)。もちろん、随所に職人ショスタコーヴィチの見事な手腕が発揮されていることも確かで、こうした新たな解釈の元で演奏の機会が増えることは大歓迎である。
西側、東側問わず“体制に迎合した駄作”という評価のためか、この交響曲の録音点数はあまり多くない。とはいえ、初演者ムラヴィーンスキイによる決定的な録音が残されているので全く不満は感じない。2種類の録音の内、どちらを取るかは好みの問題だろうが、筆者はまずムラヴィーンスキイ/レニングラードPO(Melodiya)の1984年盤を取る。これはムラヴィーンスキイ最後の録音。初演から歳月を経て最晩年に至ったムラヴィーンスキイの至高の境地が示されている。快速なテンポは相変わらずだが、そこに漂う余裕と風格が音楽をとてつもなくスケールの大きなものにしている。曲の内容を演奏がはるかに上回った、凄い演奏である。ただし、残念ながら4楽章301小節で2拍子から3拍子に変わる部分をムラヴィーンスキイが振り間違えたため、4拍子になるまでの4小節ほどの間アンサンブルが大きく乱れている。もしかしたら、この事故が以後一切録音をしなかった(させなかった?)理由なのかもしれない。なお、この演奏には映像も残されており、ヴィデオ(DML)で見ることもできる。録音系統は異なるようで音質はあまり良くないが、画像を含めてムラヴィーンスキイの映像としては最上級の部類に入る。各楽章の前に入るタイトルからみて、テレビ等で放映されたものだと思われる。カメラ・アングルも比較的多様であり、ムラヴィーンスキイの指揮の凄さを実感できる。この頻繁に拍子が変わる曲を、何と淡々と指揮していることか!これでこそ、あの怒涛のような流れが実現できるのだろう。第4楽章の振り間違いも、確認できる。もちろん、ムラヴィーンスキイ/レニングラードPO(Melodiya)の1961年盤も傑出した演奏。こちらは初演直後に行なわれた、ムラヴィーンスキイ最後のスタジオ録音。若干マスターに起因するノイズが入るが、それよりも演奏の素晴らしさに耳を奪われる。特に1楽章の狂暴な音楽には我を忘れてしまいそうだ。ショスタコーヴィチの作品としては決して良質のものではないこの曲を、尋常ならざる緊張感と完成度で聴かせる名演。
この超弩級の名演の前では他の演奏の分は悪いが、意外にもソ連国外の演奏者によるものに秀演がいくつかある。デプリースト/ヘルシンキPO(Ondine)盤は非常に格調の高い演奏。この曲の持つ複雑な表情や、狂気に満ちた音色感といったものが、実に自然に“交響曲”という形式の中に落ち着いている。全ての部分に節度が感じられ、人によっては物足りないと思う向きもあるだろうが、これだけ立派な造形力を見せ付けられるとただただ感心するしかない。ボールト/BBC SO(intaglio)盤も録音は悪いがなかなか。第1楽章の序奏部が締まりのない演奏でがっかりさせられたが、主部に入って豹変する。暴力的なまでの速いテンポ、打楽器がやや甘いものの強奏の迫力も素晴らしい。この引き締まった緊張感は、ショスタコーヴィチの本質をよく捉えている。オーケストラの技術的な限界で勝負している感じがたまらない。終演後の拍手が十分に収録されていないのが残念。ドゥリアン/ライプツィッヒ・ゲヴァントハウスO(Philips)盤は、まさしくドイツの音色だが、引き締まって颯爽とした推進力に満ちた演奏が非常に素晴らしい。この曲にはこういう行き方がよく似合う。第1楽章展開部最後の部分などで作為的なテンポ変動があるのが惜しい。これさえなければ、風格に満ちた壮麗な演奏として手放しに賞賛できただろう。
本場物では、ロジデーストヴェンスキイ/ソヴィエト国立文化省SO(Melodiya)盤が挙げられよう。ロシアン・ブラス全開、効果満点の秀演。音響的には(確かに荒い部分も多いのは事実だが)かなり優秀な出来。もちろん、内容も十分に真摯なものなのだが、やや息の短いフレージングのせいか、曲の底の浅さが妙に露呈してしまったようにも感じられる。この曲に何を求めるかで聴き手の評価も変わるだろう。
 |  |  | 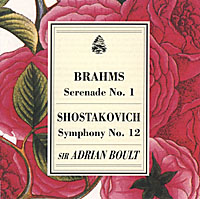 |  |  |
ムラヴィーンスキイ盤
(Victor VDC 25028) | ムラヴィーンスキイ盤
(Victor VICC 40118/23) | デプリースト盤
(Ondine ODE 846-2) | ボールト盤
(Intaglio INCD 7431) | ドゥリアン盤
(Philips 434 172-2) | ロジデーストヴェンスキイ盤
(Victor VICC-40001/11) |
 ShostakovichのHome Pageに戻る
ShostakovichのHome Pageに戻る
Last Modified 2008.05.13