![[INDEX]](./image/index2.gif)
![[INDEX]](./image/index2.gif)
1926年の秋に作曲され、同年12月2日にレニングラードで作曲者自身によって初演された。実質的なデビュー作である交響曲第1番作品10の初演は、同年3月のことであった。交響曲第1番の後、ショスタコーヴィチは西欧の新しい音楽に対する旺盛な好奇心を示し、当時の現代作曲家達(ストラヴィーンスキイ、プロコーフィエフ、ヒンデミット、クシェネックら)に大きな影響を受けた作品を作り始めることとなる。ウェーベルンの作品11とでもいうべき究極の実験作である格言集作品13、そしてこの作風の頂点となった傑作歌劇「鼻」作品15などが、この時期の代表作である。
ショスタコーヴィチ自身が後に否定することになるこの作品は、打楽器的な和音連打や極めて密なテクスチュア、不協和音程や並行的な和音進行の多用、時折登場するクラスター的効果など、この時期でなければ聴くことのできない書法に満ちている。徹底して非旋律的な曲は、翌1927年に第1回ショパン・コンクールに参加したショスタコーヴィチの卓越したピアノ技術も想像させる。
曲は単一楽章で構成されており、主に2つの主題を中心に展開されていく。中間にあるLentoの部分を緩徐楽章と見なせば、全体を3つの楽章に分けて考えることもできるが、それでも古典的なソナタ形式とは言い難い。この典型的な「怒れる若者」の作品は、ショスタコーヴィチの有り余る青春のエネルギーが爆発しているかのようなパワーに満ち、その恥ずかしいまでに無鉄砲な音楽はすがすがしい程の潔さを感じさせる。ショスタコーヴィチの初期作品を語る上で、無視できない作品だ。
この曲には作曲者自身の演奏はもちろんのこと、録音そのものの数が少ない。しかしヴェデールニコフ(Teichiku)という驚異的な名盤があり、これ一枚あれば他は全く必要ない。これは本当にとてつもない名演。最晩年(72歳)のライヴ録音とは思えない完璧な技術も凄いが、何よりも曲の価値を考えられないほど高めているその音楽的内容にはただただ驚愕する。背筋が凍りつくほどの透明感、どこか深淵を覗かされているかのような寂寥感、恐怖感。そしてロシア・ピアノ音楽になくてはならない、力強く圧倒的なタッチ。形容のしようがない、本当に凄い演奏である。ただし、残念ながらこの録音は現在入手困難であるため、同じヴェデールニコフ(Denon)の旧盤も挙げておく。これもまた極めて明晰にスコアを読みきった名演。この混沌とした曲を、完璧にまとめあげている。密なテクスチュアを形成している厖大な数の音全てに意味が感じられる。加えて技術的な完璧さも特筆すべき出来。上記ライヴ録音には劣るが、この旧録音も決して無視してはいけない傑出した演奏である。
 | 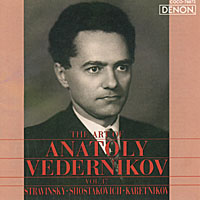 |
| ヴェデールニコフ盤 (Teichiku TECC-28170) | ヴェデールニコフ盤 (Denon COCO-78872) |
1943年2月から3月17日にかけて作曲され、同年6月6日にモスクワで作曲者自身によって初演された。1942年に亡くなった、恩師であるレニングラード音楽院ピアノ科教授レオニード・ヴラディーミロヴィチ・ニコラーエフの思い出に捧げられている。
当初予定されていた4楽章構成が3楽章に変更されるなど、この曲の作曲にはショスタコーヴィチも大分苦労したようで、自筆譜には削除や訂正が数多くなされた跡が残っているらしい。初演後の評判も低く、ショスタコーヴィチ自身もこの曲を「くずのような作品」「即興」などとして否定していたらしい。16年前に書かれたピアノ・ソナタ第1番も同様の扱いだったことを考えると、ショスタコーヴィチにとってこの曲種は不向きだったと言えるかもしれない。
第1楽章はややロンド風のソナタ形式、第2楽章は3部形式、第3楽章は変奏曲と、ピアノ・ソナタ第1番とは大きく異なって古典的な外観を保っているところが特徴的。ジダーノフ批判前の中期様式に典型的な曲の作りであるともいえよう。ショスタコーヴィチが残した数々の傑作の前ではさすがに旗色が悪いが、冷めた抒情を漂わせながらも荘厳な造形性を持っている辺り、全く無視してしまうには惜しいような気もする。
残念ながら作曲者の自演盤はないが、録音自体は決して少なくない。しかし、聴き映えのする演奏となるとギレリス(BMG-Melodiya)のライヴ盤が一番。暴力的なまでの冷徹なタッチが、何とこの曲を魅力的にしていることか!かなり早目のテンポの中で、曲に内包されている捉えどころのない感情を全て表出しきっているのにはただただ驚嘆するばかり。ライヴゆえの瑕はあるが、そんなことが全く問題にならないほどの完成度を持った音楽である。ヴォスクレセンスキイ(Triton)盤も剛毅な男臭さに満ちた名演。繊細な部分においてもスケール大きな表現力と力強さが際立ち、決してとっつき安いとは言えないこの作品を一気に聴かせてしまう。武骨な肌触りが魅力的だが、勢いに任せることなく多彩な表現が繰り広げられる、まさに完成された演奏。この系統の演奏としては他にヴァイケルト(Accord)盤も良い。一方、精緻な楽譜の読みを通して曲の真価を伝えるのはヴェデールニコフ(Denon)盤。これも完璧な名演。ただの一音もないがしろにすることなく全ての音に充実した意味を持たせた読譜力と、それを完全に音にする卓越した技術の、いずれも傑出している。ギレリスのライヴ盤の有無を言わさぬ昂奮とは対極にある、かといって単に冷徹というのではない凄い演奏。レオンスカヤ(Teldec)盤やB. ベルマン(Ottavo)盤がこの系列である。いずれも素晴らしい演奏であるが、さすがにヴェデールニコフ盤には一歩譲る。ヴォールコフ編『ショスタコーヴィチの証言』で酷評されているユージナ(Triton)盤も面白い。普通の演奏者が描ききれない幻想的かつ瞑想的な静寂を、これほど深い味わいを持って描出した演奏は他にない。テンポの揺らし方や声部の強調の仕方などに、確かにユージナの“勝手気ままな”性格の一端がうかがえるものの、これはこれで一つの芸術世界を立派に形成している。
 |  |  | 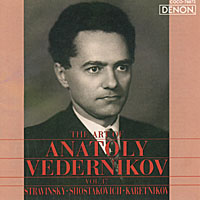 |  |  |  |
| ギレリス盤 (BMG-Melodiya 74321 40120 2) | ヴォスクレセンスキイ盤 (Triton DICC-26059) | ヴァイケルト盤 (Accord 200252) | ヴェデールニコフ盤 (Denon COCO-78872) | レオンスカヤ盤 (Teldec 9031-73282-2) | B. ベルマン盤 (Ottavo OTR C38616) | ユージナ盤 (Triton MECC-26027) |
1932年12月30日から翌33年3月2日まで、およそ一日一曲の割合で作曲された。ショパンによる同名の曲を参考にして構想されたらしい。24の調性全てが用いられ、各曲はいずれも1分前後の短いもの。歌劇「ムツェンスク郡のマクベス夫人」作品29の完成直後に着手された。ショスタコーヴィチのピアノ独奏曲としては、24の前奏曲とフーガ作品87と並んで取り上げられる機会が多い。
作品番号30番台は、前衛的な作風に傾倒した10番台と舞台作品に傾倒した20番台の特徴を残しつつも、チェロ・ソナタ作品40を経て交響曲第5番作品47に至る作品40番台の抒情的な作風を予感させる、過渡的な作品が多い。この曲は、この時期の特徴を最もよく表わしている佳品であり、続くピアノ協奏曲第1番作品35と共に人気も高い。
ショスタコーヴィチがこの曲種に手をつけたのは、これが初めてではない。レニングラード音楽院の1919年から1920年にかけて、ショスタコーヴィチは友人の作曲家G. クレメンツとP. フェーリドと各8曲ずつ持ち寄って全ての調性による24曲の全曲の作曲を計画したことがある。この計画は18曲で中断したが、ショスタコーヴィチは8曲を完成させて作品2とした。これは1926年7月15日にショスタコーヴィチ自身の演奏で初演されているが、自筆譜が紛失しているために現在では幻の作品となっている。内5曲は5つの前奏曲作品Bに収録されているという説が有力だが、確証はない。
プラウダ批判の対象となった歌劇「ムツェンスク郡のマクベス夫人」作品29とバレエ「明るい小川」作品39の間にはさまれたことと、ピアノ独奏曲という地味な曲種の故に、この曲は当初あまり注目されなかった。しかしながら、ショパンからスクリャービン、ラフマニノフと続くロシア・ピアノ音楽の系譜を継承する作品として、その評価は決して低いものではなかった。ショパン風の情緒が散見されるものの、全ては純粋にショスタコーヴィチのスタイルであり、最初期の3つの幻想的な舞曲作品5を連想させるような独特の雰囲気に満ちている。
全曲初演は1933年5月24日、ショスタコーヴィチ自身の演奏で行われた。間もなく、他人の手による各種の楽器用編曲も現われた。中でも有名なものは、ベートーヴェン四重奏団の第1ヴァイオリン奏者ツィガーノフによる全19曲のヴァイオリン&ピアノ用編曲と、ストコーフスキイによる第14番の管弦楽用編曲である。特にツィガーノフのものは原曲の雰囲気を生かしきった素晴らしい編曲で、原曲よりも取り上げられる機会が多いほど。気のきいたアンコール・ピースとして、ヴァイオリニストにとって不可欠なレパートリーとなりつつある。ストコーフスキイの編曲は、原曲に秘められたスケールの大きい重厚な音楽を、華麗なオーケストレイションで再現している。原曲の神経質で繊細な雰囲気は犠牲になっているが、興味深い編曲ではある。
この曲には録音が非常に多く、貴重なレパートリーとして人気が高いことを示している。D. ショスタコーヴィチ(Revelation)自身は抜粋しか録音を残していないが、曲の雰囲気を知る上で無視できない演奏である。全体に早目のテンポだが決して勢いに任せるような部分がなく、決して粘ったりはしないのだが、実に味わい深い抒情的な音楽である。録音が悪いので微妙な音のニュアンスは捉えきっていないが、それでも非常にきれいな音がしていることはよく分かる。同じく抜粋ではH. ネイガウス(Denon)の演奏が素晴らしい。抒情的な傾向の強い13曲が選ばれているが、ネイガウスの男らしくも品位の高い抒情性が十二分に発揮されている。技術的にも不満はない。彫りの深さは傑出しており、際立った名演に仕上がっている。実演では全曲演奏していたと言われるだけに、録音が抜粋でしかないのは残念極まりない。また、カペル(RCA)の演奏も傑出している。1944年と1945年にそれぞれ3曲ずつ録音しているが(内2つは同じ曲)、基本的に違いはない。粒の揃った切れ味の良いタッチ、鮮明で透明な響き、いずれもこの作品に相応しい。若干濃い目の表情付けをしているものの、嫌味には聴こえない。録音の鮮度が今一つなのが残念なものの、音楽的にも技術的にもほぼ理想的な演奏といえる。
全曲録音では、ヴィルサラーゼ(Live Classics)盤がこの作品のスタンダードと呼ぶに値する立派な演奏である。重く厚みがありながらも硬質な響きを持つ典型的なロシアの音色、小細工のない正攻法でスケールの大きな音楽作り、いずれをとってもこの曲の模範となる演奏と言っても過言ではないだろう。作品が持つ小粋な多彩さを、揺るぎのない枠組みの中で表出する技術と音楽性の高さには唸らされる。人工的な表情付けが全くないわけではないが、24曲全体を通した構成の確かさの中で違和感を感じさせない。一気呵成に全曲を紡ぐ熱気は、ライヴ録音の長所が存分に発揮された成果だろう。また、ムストネン(London)とニコラーエヴァ(Hyperion)の演奏も優れている。ムストネン盤は、若干エキセントリックなリズムの強調や、音量の小ささなど気になる点もない訳ではないが、全体に曲の雰囲気をよく捉えた好演。特に繊細な音色の美しさは、まさにこの曲にふさわしい。テンポ設定等の解釈も基本的に妥当なもので、安心して聴くことができる。それに対してニコラーエヴァ盤は非常に遅いテンポをとった、深い味わいを持つユニークな演奏。曲想の襞を丹念になぞっているかのような印象を受ける。美しくも重厚なタッチが、曲本来のスケールを超えた陰影を描き出している。これだけ個性的な演奏でありながらも、きちんとショスタコーヴィチの音楽に仕上がっているところが素晴らしい。他に心地好いスピード感のあるヴィアルド(Elektra Nonesuch)の佳演や、各曲毎の深い味わいといったものはあまり感じられないものの、和声とリズムの魅力がよく伝わるヴァイケルト(Accord)盤なども悪くない。
ツィガーノフの編曲版では、L. コーガン(Vn)、D. ショスタコーヴィチ(Pf)(Triton)の演奏が傑出している。これは「4つの前奏曲」と題された第10、15、16、24曲の編曲であるが、鋭利なコーガンの音色が冷ややかで淡々としたショスタコーヴィチの伴奏と共に、これらの曲の魅力を余すところなく伝えている。技術的にも文句のつけようがなく、完璧といって良い名演。コーガンには他にも異なるピアニストとの放送録音もあって同じく優れているが、とりあえずは作曲者との共演盤さえあれば十分だろう。グトニコフ(Vn)、ペチェルスカヤ(Pf)(Melodiya, LP)の4曲も、同じく立派な演奏。ロシア流儀の切れ味の良さと、やや泥臭い音色とが独特の魅力を醸し出している。安定した技術に基づいた雰囲気豊かな名演。第17番単独であればクレーメル(Vn)、マイセンベルグ(Victor)という快演もある。完璧なテクニックと弱音を巧みに使うスタイルはいかにもクレーメルらしく、この曲にふさわしいものである。異様な緊張感をはらみながらも伸びやかな歌が繰り広げられており、大変素晴らしい。一方ストコーフスキイの編曲版には、本人による4種類の演奏が残されている。中ではストコーフスキイ/シンフォニー・オブ・ジ・エアー(EMI)の1958年盤が良い。ストコーフスキーが死の前年に残したナショナルPOとの1976年盤に比べるとかなり録音は悪いが、ストコーフスキイの意図したところが最もよく出た佳演。よく歌う弦楽器と壮麗な管楽器が、原曲にはない華麗な雰囲気を描出している。一方ストコーフスキイ/ロイヤルPO(Music & Arts)の1969年ライヴ盤も、かなりノイズが気になる録音ではあるが、内容は非常に充実している。極めてスケールの大きい、かつ引き締まった迫力ある演奏は、ストコーフスキイのこの曲の録音中最も魅力がある。
 |  |  |  |  |  |  |
| D. ショスタコーヴィチ盤 (Revelation RV70007) | H. ネイガウス盤 (Denon COCQ-83666) | カペル盤 (RCA 09026-68992-2) | ヴィルサラーゼ盤 (Live Classics LCL 306) | ムストネン盤 (London POCL-1106) | ニコラーエヴァ盤 (Hyperion CDA66620) | ヴィアルド盤 (Elektra Nonesuch 79234-2) |
 |  |  |  |  |  | |
| ヴァイケルト盤 (Accord 202812) | L. コーガン盤 (Triton DMCC-24026) | グトニコフ盤 (Melodiya 33 D 010223-24, LP) | クレーメル盤 (Victor VICC-2077) | ストコーフスキイ盤 (EMI ZDMB 5 65427 2 3) | ストコーフスキイ盤 (Music & Arts CD-847) |
1950年7月、ショスタコーヴィチはライプツィヒで開催されたバッハ没後二百年祭にソ連代表団長として参加した。閉会式の最後に、タティヤーナ・ニコラーエヴァ、マリヤ・ユージナ、パーヴェル・セレブリャコーフによる、J. S. バッハの三台のピアノのための協奏曲ニ短調が演奏されることになっていたが、ユージナが指を痛めて弾けなくなったというアクシデントがあり(『証言』などに紹介されている彼女の行動パターンからすると、本当に指を痛めたのかどうか怪しいところだが)、急遽ショスタコーヴィチが第二ピアノを担当するというハプニングもあった。
当初はこの記念祭に参加するための旅行の途上、自身のピアノ演奏技術を完成させるための多声的な練習曲として着想されたようだが、記念祭出席を通して受けた印象を元に構想が拡大され、J. S. バッハの平均律クラヴィア曲集を範とする大規模な作品としてまとめられた。1950年10月から翌51年2月にかけて作曲され、1951年4月5日の作曲家同盟交響曲部門の会合の席上、ショスタコーヴィチ自身の演奏で抜粋が演奏され、全曲初演はバッハ没後二百年祭記念コンクールの優勝者タティヤーナ・ニコラーエヴァによって1952年12月23日と28日の2日間で行われた。
ショスタコーヴィチ自身による初演の直後に行われた1951年5月16日の作曲家同盟主催の合評会では、いつもながらこの曲に対して批判的な意見が数多く出された。1948年のジダーノフ批判の路線上にあった当時は、“理想主義的傾向”や“形式主義的傾向”にあるとして厳しい批判が浴びせられたようだ。しかしながら、ユージナやニコラーエヴァといった演奏者は、ソヴィエト・ピアノ音楽に新たなレパートリーが加わったことを積極的に評価し、この曲の普及に貢献した。
この曲は、ショスタコーヴィチの全ピアノ作品中で最も優れた傑作である。さらに、ロシア・ソヴィエトの全ピアノ作品の中でも特別な位置を占める作品でもある。古典的な形式と伝統を真性に継承しつつも、徹底して現代的である。24の異なる調性全てを使い、各曲は極めて多彩な表情を持っていながら、全体の均等性と統一性が見事に図られているところに、ショスタコーヴィチの天才の一端を垣間見ることができる。全体の曲調は穏やかで平明な雰囲気が支配的だが、時折凶暴なまでの力強さが押し出されたり、深く物思いに沈むような瞑想的な平静さが漂ったり、荘重な抒情が感動的だったりと、息をつく暇もない。また、オラトリオ「森の歌」作品81の主題がところどころ顔を出すのは、ジダーノフ批判以降の中期作品の特徴でもある。個人的に好きなのは第15、4、24番辺り。特に第15番は、全曲中で最もショスタコーヴィチの個性が際立った名作だと思う。
本作品には、作曲者自身の録音がいくつか残されている。中でも1958年に録音されたD. ショスタコーヴィチ(EMI)盤を、まず聴いて欲しい。これは全曲からの抜粋(第1、4、5、23、24番)だが、これほどまでに哲学的な演奏はないだろう。選ばれている曲の性格も相まって、極めて崇高さを感じさせる深遠な演奏が繰り広げられている。人間の情感よりは、むしろ神の領域に属するような広がりと深みをもった名演。この24番を聴いた後では、しばらくは他の音楽を耳にしたくなくなる。ショスタコーヴィチ自身による他の録音は、全体的な雰囲気はともかく、技術的に問題のある箇所が多く、ファースト・チョイスとしてはお薦めできない。
通して演奏すると3時間弱を要する曲だけに全曲盤はそれほど多くないが、初演者ニコラーエヴァ(Hyperion)による決定盤が存在するので全く不都合はない。彼女は計3回この曲を録音しているが、これはその最後のもの。ただし、第2回目の録音とは3年しか間隔が空いていないため、演奏内容はほぼ同じと言っても良い。1回目の録音に比べるとテンポは遅くなっているが、技術的な不安とは無関係で、各曲を丹念に弾き込んだ結果であることは明白である。落ち着いた中にも精神の力強さは失われず、全く弛緩することなく深い味わいを漂わせている。各曲の多彩さを生かしながらも、長大な全曲の統一感を失っていないのも見事。
全曲から何曲か抜粋した形での録音の中では、リヒテル(Philips)(第14、17、15、4、12、23番)とグリンベルグ(Triton)(第7、8、11、13、14、15、17番)の両者が双璧。リヒテルには時期の異なる録音がいくつか存在しているが、1963年のこの録音は最も状態のよいもの。巨大な風格と瞑想的な抒情性、形容のできない寂寥感、いずれをとってもこれらの曲の真価をこれ以上ない形で伝えている。技術的な完璧さや、美しくも強靭なロシアの音色もさることながら、曲の内容を把握しきった理想的な表現は圧倒的。特に第15番はとてつもない名演。リヒテルによるこの曲集の録音中、最高の出来といえよう。このスタジオ録音と同時期に行われたキエフでのライヴ録音(第4、12、23、14、17、15、8番)も凄い。ライヴながらもコンディションが良かったのか、気になるようなミスは皆無。Philips盤の完成度に、さらなる内面の燃焼度を加えたような名演。録音の鮮度がいまひとつなのが非常に残念。一方、グリンベルグも大変素晴らしい。ありとあらゆる感情が、ショスタコーヴィチの音楽を通して表現されている。強靭で暖かいタッチの美しさと、フーガの処理の的確さ、そして理想的なイントネーション。いずれをとっても最高の演奏である。僕の大好きな第15番も巨大な演奏。リヒテルとは違った魅力がある。録音は良くないが、絶対に聴いておきたい。この両者にはやや劣るが、ギレリス(Testament)(第1、5、24番)も充実した表現力を持つ魅力的な演奏。どんなに繊細な箇所でも決して神経質にはならず、あくまでも骨太な男っぽい音楽となるところが個性的。作品の現代性よりは古典性をより重視した解釈となっている。
 |  |  |  |  |  |
| D. ショスタコーヴィチ盤 (EMI CDC 7 54606 2) | ニコラーエヴァ盤 (Hyperion CDA66441/3) | リヒテル盤 (Philips PHCP-5245) | リヒテル盤 (tnc CD-H1469-70) | グリンベルグ盤 (Triton DMCC-24051) | ギレリス盤 (Testament SBT 1089) |
ショスタコーヴィチ最初期の代表作。ショスタコーヴィチの作品中、最初に出版されたものである。レニングラード音楽院時代の1920年12月4日に作曲され、ピアノ科の友人イオシフ・シュヴァルツに献呈された。公式初演は1925年3月20日で、ショスタコーヴィチ自身の演奏による。なお、この演奏会はショスタコーヴィチの作品ばかりで構成された商業演奏会で、他にピアノ三重奏曲第1番なども演奏され、姉マリーヤも出演したらしい。
簡潔な3曲から成るこの曲は、和声とリズムの扱いにおいて、すでに後年のショスタコーヴィチを予感させるもので、単なる資料的な価値を超えて十分に魅力的なものである。
この曲には、作曲者自身の演奏が少なくとも3種類残されている。録音データが入り乱れていて多少の混乱はあるものの、最も優れた演奏は1947年盤(D. ショスタコーヴィチ(Melodiya/Revelation))である。リズム・テンポ・音色、いずれを取っても最高の演奏。録音は非常に悪いが、これ以上雰囲気の良い演奏は他にない。他の録音も感じは悪くないが、技術的に崩壊しているためにファースト・チョイスとしてはお薦めできない。
本作品の初録音となったジョイス(Pearl)盤も素晴らしい。切味の良い技術を遺憾なく発揮し、美しい音色で振幅の大きな音楽を奏でている。ただし、録音は悪い。他にもオルティス(EMI)やペンティネン(BIS)などが好演を残しているが、ニコラーエヴァ(Hyperion)盤が個性的な演奏で注目される。技術的な問題は全くなく、美しく深いタッチで奏でられたきれいな演奏。ただ、遅めのテンポでどこか哲学的な表情を漂わせているところが非常にユニーク。この曲が本来持っている素朴な風情があまり感じられないため、好き嫌いは分かれるかもしれない。
また、この曲には数種類の編曲があるが、グリークマン(ショスタコーヴィチの友人イサークと別人であるかどうかは、よく分からない)によるヴァイオリン&ピアノ用編曲が比較的有名。ドゥカン(Vn)、コシェ(Pf)(プライヴェート盤)がこの編曲については最高の演奏だろう。ドゥカンの細身の音色が曲の雰囲気に非常によく合っている。変な気取りはないが、どことなく高雅な気品漂う歌い回しは絶妙。プライヴェート盤のために入手困難なのが残念。D. オーイストラフ(Vn)、バウアー(Pf)(Kultur)によるヴィデオ(モノクロ)もなかなか良い。ゆったりとしたテンポで実に自然に、楽しく音楽が流れていく。技術的にも完璧。太く暖かい音色が、大人の雰囲気を醸し出している。第2曲だけであれば、ハイフェッツ(Vn)、ベイ(Pf)(RCA)による非常に切味鋭い、ヴィルトゥオージックな演奏もあり、その鮮やかさには感心させられる。ただ、初期ショスタコーヴィチ独特の雰囲気は犠牲にされている。これをどう評価するかは、聴き手の趣味の問題だろう。
 | 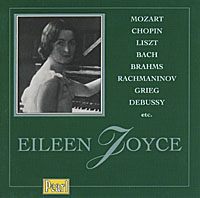 |  |  |
| D. ショスタコーヴィチ盤 (Melodiya MCD 008) | ジョイス盤 (Pearl GEMM CD 9022) | オルティス盤 (EMI 7243 5 73518 2 9) | ペンティネン盤 (BIS BIS-CD-276) |
 |  |  |  |
| ニコラーエヴァ盤 (Hyperion CDA66620) | ドゥカン盤 (P1119) | D. オーイストラフ盤 (Kultur 1208, Video) | ハイフェッツ盤 (RCA 09026-61766-2) |
ショスタコーヴィチの長女ガリーナのために、1944年から1945年にかけて作曲された。初演は、その冬に行われた作曲家同盟主催の子供の演奏会で、ガリーナの演奏によって行われた(ただし第6曲まで)。
この曲は「マーチ」「ワルツ」「くま」「楽しいおはなし」「悲しいおはなし」「ぜんまいじかけのお人形」「誕生日」の7曲から構成されている。第6曲「ぜんまいじかけのお人形」の主題はスケルツォ嬰ヘ短調作品1から引用されており、第7曲「誕生日」の主題は後に祝典序曲作品96に使われた。自筆楽譜および初期の出版譜には第7曲が収録されていないが、作曲者自身の作品目録では第7曲も作品69として入れられている。各曲は難易度が低いものから順に並べられており、娘のピアノのレッスンを想定していると考えられ、大変微笑ましいものがある。
この曲には作曲者自身による録音(D. ショスタコーヴィチ(Revelation))が残されている。出版譜とは第3曲と第5曲の順番が入れ替わっている。あっけないほどあっさりとした快速なテンポの中に、愛らしく快活な表情がにじみ出ている。子供と一緒に楽しみながら弾いている情景が目に浮かぶような演奏。録音は非常に古いが、この曲の精神が最良の形で表現されている。また、ショスタコーヴィチ自身が各曲のタイトルを読み上げているのも楽しい。またボブリツカヤ(Le Chant du Monde)盤も、基本的に余計なことはせず、丁寧に音楽を奏でているのが大変好ましい。安定した技術で、何の不満もなく音楽を楽しむことができる。本作品の録音は、他にボブリツカヤの旧録音(Melodiya)がLPで残されているだけだが、そもそも聴くための作品というよりは自分で弾いて楽しむ類いの作品であるだけに、上記2種類の録音があれば全く不満はない。
 |  |
| D. ショスタコーヴィチ盤 (Revelation RV70007) | ボブリツカヤ盤 (Le Chant du Monde LDC 288 034) |
子供のノート作品69の7年後、1952年に再び長女ガリーナのために作曲された作品。初演等の記録は残っていない。「抒情的ワルツ」「ガヴォット」「ロマンス」「ポルカ」「ワルツ=スケルツォ」「手回しオルガン」「ダンス」の7曲からなるこの曲は、第7曲を除いて全て初期の舞台作品をピアノ独奏用に編曲したものである。詳細は次の通り:第1曲(「明るい小川」より;バレエ組曲第3番第5曲)、第2曲(「人間喜劇」より;バレエ組曲第3番第2曲)、第3曲(「明るい小川」より;バレエ組曲第1番第3曲)、第4曲(「明るい小川」より;バレエ組曲第1番第2曲)、第5曲(「ボルト」より;バレエ組曲第1番第5曲)、第6曲(「明るい小川」より;バレエ組曲第1番第4曲)
この種の曲としては、子供のノート作品69よりも取り上げられる機会が多い。いずれも親しみやすい曲ばかりで、別の作品の中で他の編成用にも編曲されている曲が多い。各曲の初出を見ると発表当初は厳しく批判された作品ばかりが並んでいるところに、どこか皮肉めいたものを感じる。
この曲の録音は決して少なくないが、チモフェーエヴァ(Victor)盤さえあれば十分である。これは理想的な名演。余計な味付けを排しながらも、作品が本来持っている愉悦的な雰囲気を鮮やかに表出しているのが見事。音色そのものも典型的なロシアン・サウンドで魅力的。第7曲だけであれば、ボブリツカヤ(Le Chant du Monde)盤も素晴らしい。
 |  |
| チモフェーエヴァ盤 (Victor VICC-2092) | ボブリツカヤ盤 (Le Chant du Monde LDC 288 034) |
1922年2月24日、ショスタコーヴィチが15歳の時に父ドミートリィ・ボレスラーヴォヴィチが46歳の若さで急死した。このことは単に家族を悲しませただけではなく、深刻な経済的困窮をショスタコーヴィチ家にもたらした。ショスタコーヴィチ自身も映画館で伴奏ピアニストのアルバイトをして家計を助けたりしたが、長女マリーヤが音楽院を卒業して就職するまでこの状態は続いた。加えてショスタコーヴィチの健康上の問題もあり、非常に辛く苦しい時期だったようである。
「前奏曲」「幻想的舞踏」「夜想曲」「終曲」の4つからなる本作品は、父ドミートリィ・ボレスラーヴォヴィチの思い出に捧げて1922年3月に作曲された。初演は1925年3月20日、モスクワ音楽院小ホールにおいて作曲者自身とレフ・オボーリンによって行われた。ただし、この編成は明らかに姉マリーヤと一緒に演奏することを念頭においていると考えられ、2人で父を追悼しながら演奏されたであろうことはまず間違いのないところであろう。
曲はロシア風の甘美な抒情に満ち、感傷的で美しいものである。加えて、形式の巧みな取り扱いと個性的なリズムの感覚(特に第2曲)に、ショスタコーヴィチの個性が強く認められる。全体に悲劇的な調子が支配的なのは当然だが、その中に多様な感情が聴き取られるところに、この早熟の天才の非凡さがある。文句なしに魅力的な作品であり、ショスタコーヴィチがロシアの作曲家であったことを再認識させる作品でもある。
この曲には自演盤がない上に、決定的な名演というのもない。模範的な演奏としてはタニュエル&ブラウン(Chandos)盤が挙げられる。作為的な部分は一切なく、楽譜の内容が素直に表出されている。安定した技術で全てが整然とまとめられているが、リズムや和声に見られるショスタコーヴィチの個性も見事に処理している。加えて、本作品に特徴的な甘い抒情も嫌味にならない程度に盛り込まれており、全く不満はない。この他に暗く劇的な表情を持ったA. & L. Totsiou(Lyra)の好演、LPしかないがロシア風の甘い節回しよりも、ショスタコーヴィチらしい乾いた響きを重視しているポーストニコヴァ&ペトローフ(Melodiya、LP)盤なども、あっさりとした音楽の運びに妙な思い入れの感じられないところが素晴らしい。
 |  |  |
| タニュエル&ブラウン盤 (Chandos CHAN 8466) | A. & L. Totsiou盤 (Lyra ML 0183) | ポーストニコヴァ&ペトローフ盤 (Melodiya C10 18471-2, LP) |
交響曲第10番作品93と前後して、1953年に作曲された作品。当時モスクワ音楽院でピアノを学んでいた長男マクシームのために作られた。おそらくピアノ協奏曲第2番作品102と作曲の動機・目的は同じなのであろう。初演は、マクシームと彼の学友マロレトコーヴァによって行われた。
ショスタコーヴィチが息子を溺愛していたことは有名で、この曲にはそうした“家庭的な”側面が反映していると考えられる。この単一楽章による短い曲はいかにも大家の余興といった雰囲気で、ソツのない構成の中にリラックスした穏やかな感情が流れている。他の傑作と比較するといかにも軽いが、気の効いた小品として相応の価値を持っていると言うことはできるだろう。交響曲第10番以降、交響曲第11番作品103までの作品群はいずれも同じような雰囲気を持っており、ショスタコーヴィチの創作歴の中でも特徴的な時期となっている。これをスターリン死後の「雪解け」と関連づけるのも、あながちはずれているとは言えないだろう。
初録音は親子で行われた。そのD. & M. ショスタコーヴィチ(Victor)盤は、強い低音の響きにのった引き締まったリズムが素晴らしい。全体の見通しや構成感も非常に良いので、全く退屈することなく聴き通せる。録音は悪いが、この曲の理想的な演奏。この演奏と同じレベルの出来で、録音がマトモなのがタニュエル&ブラウン(Chandos)盤。一般的にはこちらの方が薦められるだろう。他に、デュオ“ライネ・エリザベス”(Discover)盤が派手さはないものの、堅実なアンサンブルと引き締まった解釈が立派な演奏。テンポ設定も無理がなく、安心して聴くことができる。強奏部に物足りなさは残るものの、全体に素朴な美しさが漂っているのが好ましい。
 |  |  |
| D. & M. ショスタコーヴィチ盤 (Victor VICC-2048) | タニュエル&ブラウン盤 (Chandos CHAN 8466) | デュオ“ライネ・エリザベス”盤 (Discover DICD 920150) |
Last Modified 2008.05.14